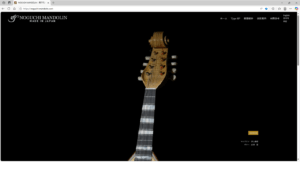今年は午年。あっという間の一カ月、まさに馬の如く俊足で軽やかな時間でした。
馬力とは「75kgの重さを、1秒間で1メートル持ち上げる力」だそうです。
馬、一頭の種発力はこの10倍近くあるそうです。
人間が一人で行えることは、限りがありますが、馬の力にあやかって、知恵を絞って10倍、20倍にしていけるよう、チャレンジしてきたいところです。
小学校低学年のころ、近所にあった大学の乗馬クラブに勝手に寄り付き、餌をやったり体を洗ってあげたり、当時の大学生に教えてもらいながらお世話をしていたことが、馬が好きになった理由です。それぞれの馬の性格も違い、やさしい性格、気性の荒い性格、のんびりした性格と個性豊かでした。とても綺麗で凛々しくて憧れていた記憶が蘇ってきます。
「馬には乗ってみよ、人には添うてみよ」
ということわざにもあるように、いつかは馬に乗ってみたいと思うのです。何事も経験してみなければ本当の事はわからないので、何もしないで判断したり評価したりせず、実際に試して判断する事が必要かと・・
人とは親しく交際してみなければ相手の善悪を判断することなく、先入観での判断をなくし、寄り添ってみることで道が開けるとおもわれます。
馬のように躍動感をもって前進を続けて参る所存です。